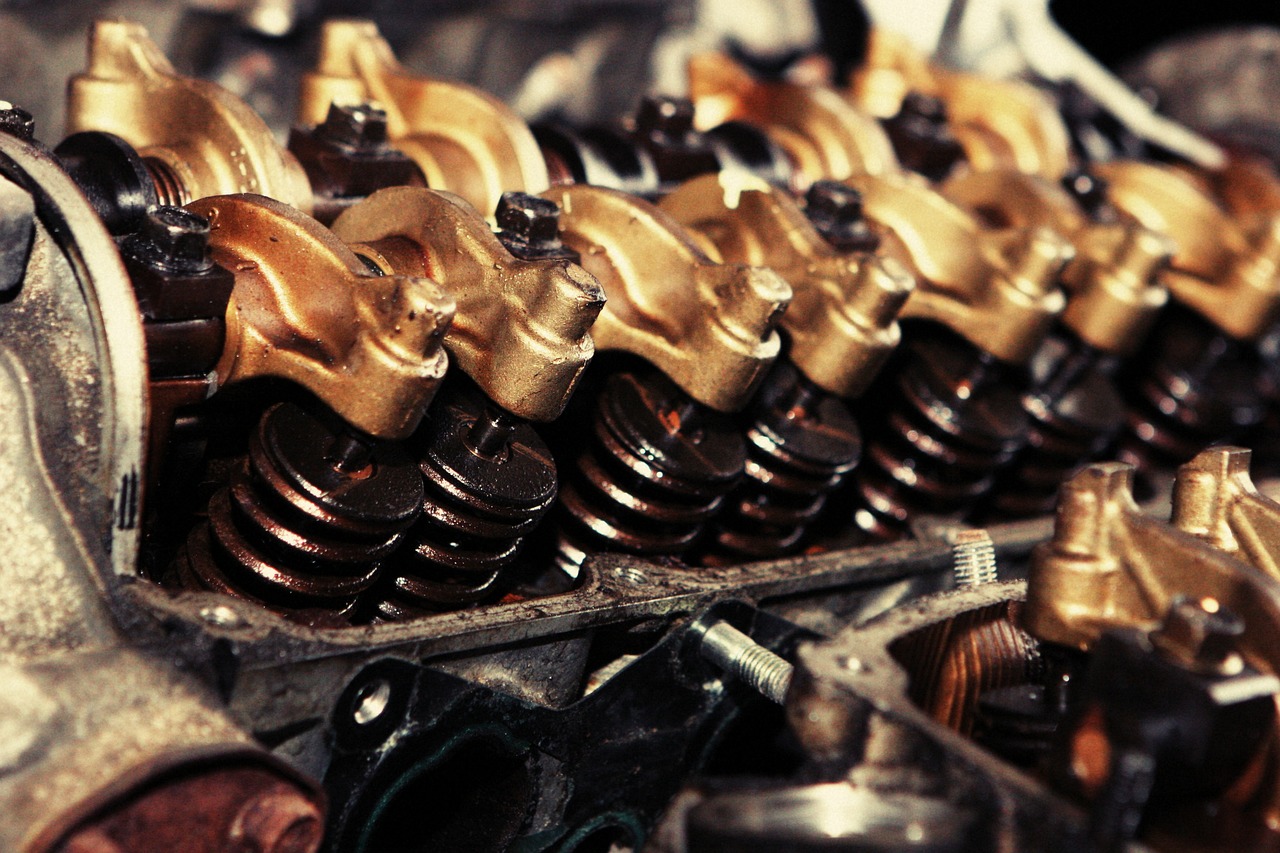わざとらしさ
ブラームスのピアノ協奏曲第1番は、数多くあるピアノ協奏曲の中でも、特に僕にとっては特別な作品です。なぜ特別なのか、長々と説明するつもりはありませんが、一言で言うなら「格別」。この曲には、心を揺さぶる魅力的な要素が散りばめられていて、喜びや陶酔感に浸れるひとときがあります。
この作品は、若かりしブラームスが試行錯誤の末に完成させたものですが、その点で彼の交響曲第1番と似ているかもしれません。さらに、初演時には全く評価されなかったというのも驚きです。『春の祭典』のように前衛的ならともかく、このように美しく味わい深い作品がなぜ不評だったのか、理解に苦しみます。今でもこの曲の価値に見合う人気があるとは言い難いですし、少しとっつきにくいのは確かですが、その「万人受けしない」点こそが、ブラームスの魅力なのかもしれません。
一つ言うなら、長すぎるのがネックだったのかもしれません。実際、今でも演奏される頻度は少なく、演奏家や主催者にとっては敬遠される傾向があるようです。ピアノコンクールでこの曲を選んでしまうと優勝できない、というジンクスまであるそうで、それも長すぎるのが理由のようです。
そんなブラームスのピアノ協奏曲第1番が、先日放映されたNHK音楽館で取り上げられていました。パーヴォ・ヤルヴィ指揮、ドイツ・カンマーフィルハーモニーの演奏で、ピアノはドイツの中堅ラルス・フォークトが担当しました。演奏会場はオペラシティコンサートホールです。
正直、フォークトのピアノは僕の好みではありませんし、ドイツ・カンマーフィルもあまり注目していなかったので期待していませんでしたが、それでも「ブラームスの第1番」と聞けば見ないわけにはいきません。
予想通り、演奏は僕の好みとはかけ離れていました。普段なら10分でやめてしまうところですが、それでも最後まで聞き続けたのは、この曲そのものの魅力があったからだと思います。
ドイツ・カンマーフィルの演奏は、正直言って魅力がよく分かりませんでした。耳慣れの問題もあるのかもしれませんが、ブラームスをこんな軽い響きで演奏されると、どうしても不満が募ります。最近は、室内オーケストラが増えているようですが、これは音楽的な必然なのか、それとも大オーケストラの運営上の問題から生まれた流れなのかは分かりません。ただ、僕はブラームスには柔らかくて重厚な、大人の情感が感じられる響きを求めてしまいます。
それ以上に理解に苦しんだのが、フォークトのピアノでした。以前もベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番で彼の演奏を聴いたことがありますが、その時以上に違和感がありました。彼の演奏は、聴く人を作品の世界に引き込むというより、ステージ上で自分ひとりが何かと格闘しているようにしか見えません。
音の分離も、要所での歌い込みもなく、厚みのあるハーモニーも感じられないのに、フォルテだけが強調されて音が荒れてしまう。スタインウェイという強靭なピアノでも、彼の粗雑な強打には耐えきれず、音が割れてしまったのには驚きました。
さらに驚いたのは、演奏後にホワイエで行われたヤルヴィとフォークトの対談のシーンです。この二人は長い付き合いだそうですが、自然な会話に見せかけているものの、どう見ても事前に用意された台本があるようで、僕には完全にやらせにしか見えませんでした。
今やクラシック音楽家も、カメラの前では俳優のような演技が求められる時代になったのかと思うと、なんだかみんな音楽以外のことにエネルギーを注いでいるようで、時代の変化を強く感じました。